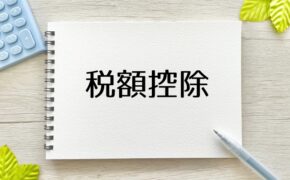地震の備え
「モノ」の備えだけで大丈夫?備えてあんしん地震の話① ~罹災証明書~
こんにちは! リンクジャパンです。
年始に能登地域を襲った地震からもうすぐ2か月が経とうとしています。
今回の地震をきっかけに食べ物やお水を準備してみたり、地震保険を考えてみたりなど、地震が起きてしまった時の備えを考えた方も多いのではないでしょうか?
こうした「モノ」の備えも大切ですが、「知識や情報」も大切です。
今回から数回に分けて、「モノ」の備えではなく、万が一被災した場合に助けになる「知識や情報」を紹介していきます!
初回は「罹災証明書」についてお話します。
💡「罹災証明書」とは??
地震に限らず、異常気象による大雨や暴風などの自然災害で住宅が被害を受けた時に、自治体から発行される証明書です。
災害後に行政が被災者へ支援を行う際に、どの程度の支援か必要なのか判断するのにとても大事な書類で、住宅の損害の状況に合わせて、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損」の4種類があります。
また、行政からの被災者生活再建支援金や義援金などの金銭的支援を受けられるだけではなく、
・税金や各種保険料、公共料金の免除や支払い猶予
・仮設住宅の支給
・住宅金融支援機構による被災者向けの低金利融資
などの支援を受けられるようになります。
💡「罹災証明書」を取得するには??
自治体に申請し発行してもらいます。
地震などの広域災害の場合、震源地付近を一括で「全壊」とする場合もありますが、基本的には自治体へ申し出することによって発行が進められます。
申請期限は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体の期限を確認しておきましょう。
職員が現地に来て建物の状態を確認する場合もあれば、住民の写真に基づいて認定を進める場合もあります。
万が一被災した場合、安全を確認できてから片付ける前に、家の中や外観の写真を撮っておくことをおすすめします。
💡「罹災証明書」の注意点は??
外観上で損害を判定する「一次調査」と、外観に加えて住居内を確認する「二次調査」があり、外観上で「半壊」と認定された場合でも、その後の二次調査でより重い損害と認定される場合があります。
この二次調査は必ず申請が必要なので、一次調査の認定が思ったより軽いと感じた場合は、二次調査を申請をしてみることをおすすめします。
この二次調査を行う場合にもやはり写真を参考にすることがあるので、写真はたくさん撮っておくほうが良いですね。
万が一被災した際に、「罹災証明書」は色々な支援を受けるために必要な証明になる、ということを覚えておきましょう!